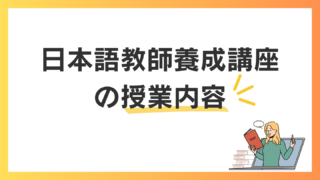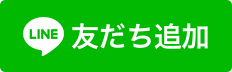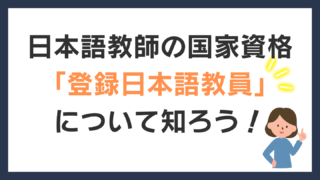私たちが使っている「日本語」は、どんな言語なのでしょうか。
日本語が母語である私たちは、普段無意識に日本語を使っているので、日本語がどのような言語なのか、またどのような特徴を持っているのかを考える機会は少ないと思います。
この記事では、私たちが普段使っている日本語という言語の特徴について、他の言語と比較しながら、簡単に説明したいと思います。
・世界の中での日本語の位置づけ
・日本語の言葉や文法などの特徴
世界の中での日本語

まず、世界の言語の中から見た「日本語」について紹介します。
言語の数え方は、方言をどこまでカウントするか等によって様々な方法がありますが、世界には約6,900の言語が存在すると言われています。
使用者数が最も多いのは中国語で、スペイン語、英語が続きます。
日本語は1億2500万人以上に使用されており、世界の中で見れば10番目前後と、使用者数の多い言語になっています。
国際交流基金の2021年度「海外日本語教育機関調査」によると、世界の日本語学習者数は約380万人となっており、
中国、韓国などの東アジア地域が約170万人、インドネシア、ベトナムなどの東南アジア地域が約120万人と最も多くなっています。
また、文化庁の「国内の日本語教育の概要」によると、日本国内の日本語学習者数は、約16万人となっています。
こちらもアジア地域からの学習者が最も多くの割合を占めています。
日本語の特徴

次に、日本語が持っている言語的特徴について、いくつか例を挙げて紹介します。
日本語の語順
日本語はSOV型と言われ、
「私は(S)日本語を(O)勉強します(V)」
のように、基本的には動詞や形容詞などの述語が一番最後に来ます。
韓国語、モンゴル語、オランダ語などもこの形で文が作られます。
対して、英語やスペイン語、中国語などは、
「I(S) study(V) Japanese(O)」
のように、主語のすぐ後ろに動詞や形容詞などが来て、そのあとに目的語がくるSVO型と呼ばれます。
ただ、日本語は比較的語順が自由な言語で、「(私は)明日休みます」のように(S)が省略されたり、「カレーが好き、私は」のように語順が入れ替わることも珍しくありません。
日本語の音声
日本語の母音は「ア、イ、ウ、エ、オ」の5種類です。
他の言語と比べてみると、ベトナム語は11個、韓国語は8個、フランス語は6個など、日本語の母音の数はあまり多くありません。
また、他の言語は複母音といって、複数の母音を組み合わせて新たな母音を作る場合もあるのですが、日本語は基本的に「1つの子音+1つの母音」で1つの音が構成されています。
(例)「か」→「K」+「A」=「KA」
日本語の音声についてもっと知りたい方はこちら↓
日本語のモーラ(拍)
例えば英語の「drink」は母音が1つ(i)しかないため、音節(音のまとまり)が1つ、と考えられます。
しかし、日本語の「ドリンク」は「ド・リ・ン・ク」と4つのモーラ(拍)があると考えられます。
1文字に1つの音がある、というイメージです。
これは非母語話者にはなかなか難しく、外国人がこの「ドリンク」という言葉を聞いて書き起こすと、「ドリク」のように、「ン」が抜けてしまったりすることがよくあります。
長音「ー」、促音「っ」などが含まれている場合でも、このようなことは頻繁に起きます。
「実感(じっかん/4拍)」と「時間(じかん/3拍)」
「おばさん(4拍)」と「おばあさん(5拍)」
などの違いは、外国人学習者が聞き分けや書き分けに苦労するところの1つです。
日本語の文字
日本語では、基本的にひらがな、カタカナ、漢字の3種類の文字が使われますし、それに加えてアルファベットもよく使われますよね。
世界の中で見ても、日本語は文字数の多い言語と言えます。
例えば、英語はアルファベット26文字ですべてを表しますし、ハングルは24文字。
それに対して、日本語はひらがなだけでも、(「きゃ・きゅ・きょ」などの拗音や「が・ざ・だ」などの濁音、「ぱ」などの半濁音を除いて)46文字あります。
それと同じだけのカタカナもあり、漢字は小学校で習うものだけでも1000文字を超えます。
これだけの文字数を使う言語は、世界的にも珍しいといえます。
このあたりが、非漢字圏の学習者にとって、日本語が難しいと言われる理由の1つと言えるでしょう。
文字を覚えるだけでも、一苦労なんですよね。
日本語の文字と表記についてもっと知りたい方はこちら↓
まとめ
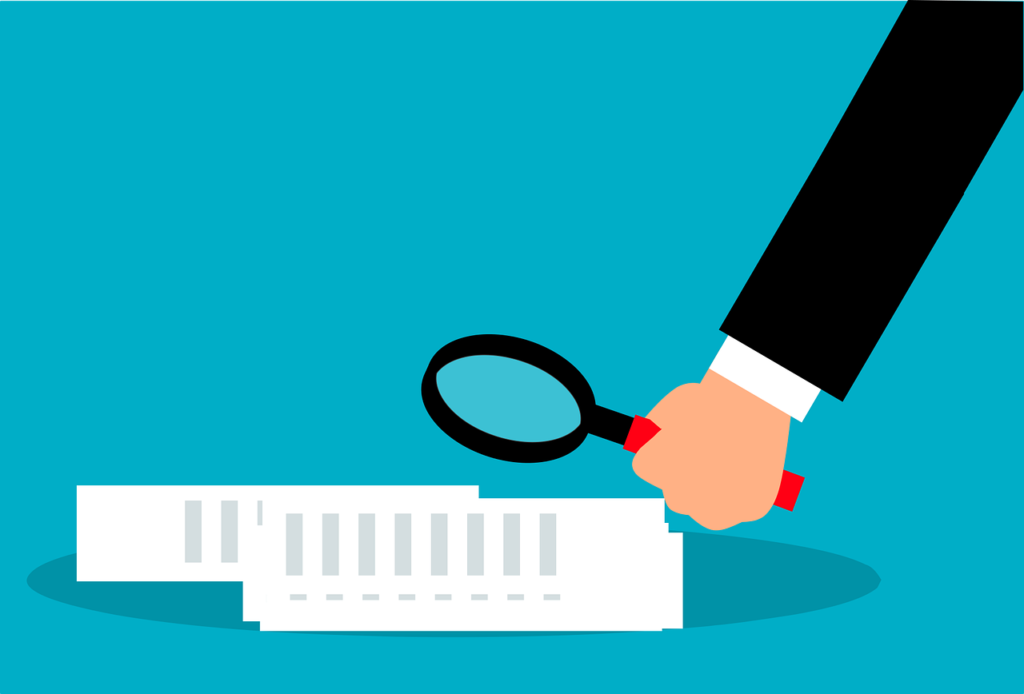
日本語の特徴が少し分かっていただけたでしょうか。
日本語には、他にもユニークな特徴や、面白い特徴がたくさんあります。
普段意識しないからこそ、改めて考えてみると、面白い発見がたくさんあるんですよね。
もっと日本語について知りたい!勉強してみたい!という方は、ぜひ当校の
日本語教師養成講座の受講を検討してみてください。
まずは無料説明会へお越しください。詳しい講座の内容をご説明します。
日本語教師を目指していない人でも、大歓迎です🏫
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事に関する疑問や、養成講座の内容等についてのご質問は、いつでもお気軽にこちらのページからお問い合わせください。